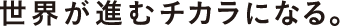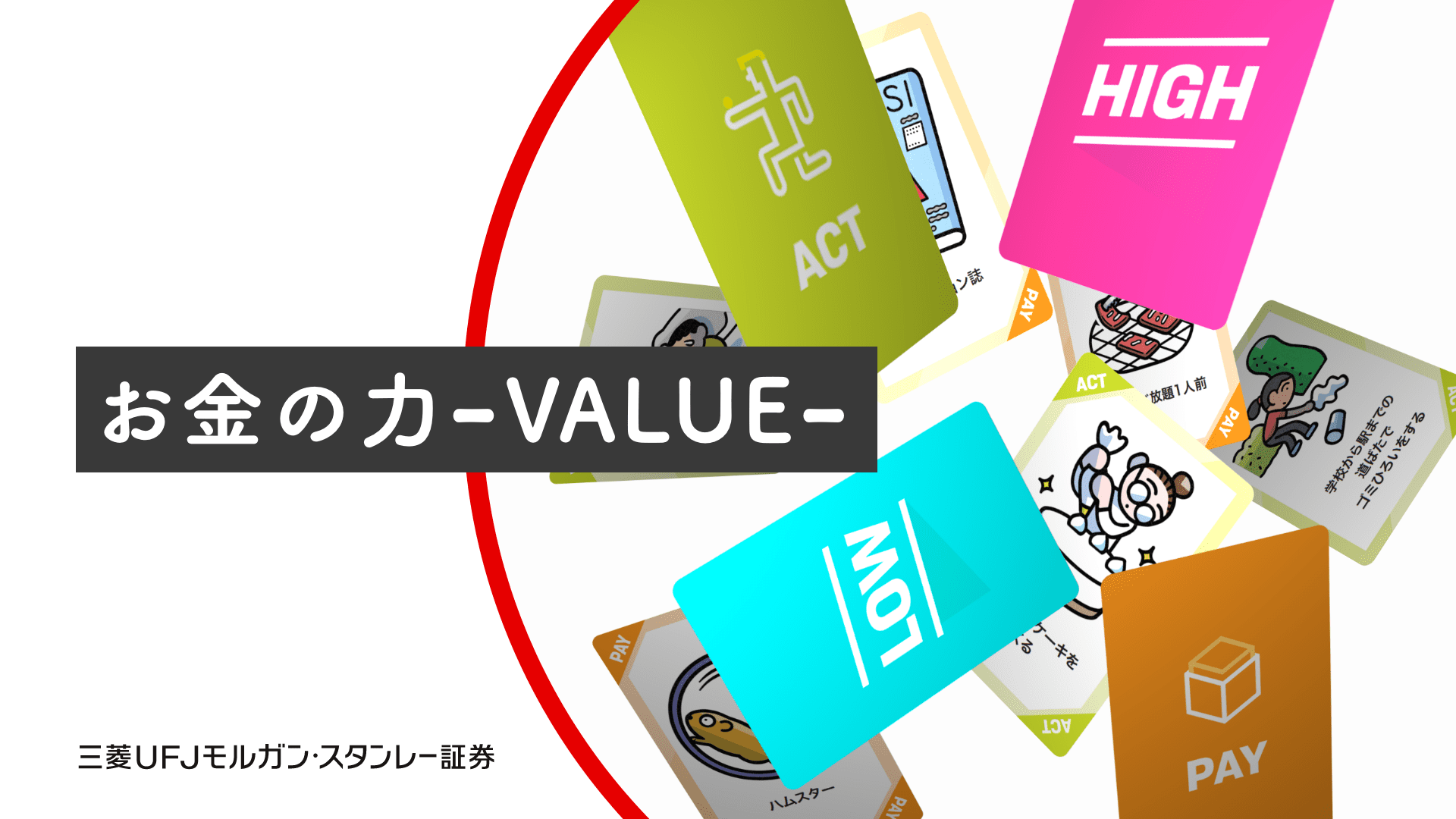今回「お金を活かす力」を身につける小学生のための探究イベント「MONEY GENIUS 2025春」を虎ノ門ヒルズにあるCIC Tokyoにて開催しました。当日は小学校5・6年生のお子さんと保護者の総勢40組が参加。それぞれ子どもたちが3~4名のチームに分かれて、「VALUE」「LOOP」(今回のイベントのために開発した特別なプログラム)という2つの探究型ゲームを体験しました。
REPORT
アイスブレイクとチームビルディング

まずは自己紹介からスタート。通常の学校でのプログラム開催と異なり、初対面同士での参加となる子どもたち。「緊張しています」「帰ってゲームをしたい」といった率直な気持ちを共有する姿が見られる中、続いて行ったのは、簡単な連想ゲームを通じたチームビルディング。
「白と黒の動物といえば?」「ペットといえば?」など、チームで回答を揃えるゲームを通して、徐々に笑顔と会話が生まれ、和やか雰囲気を生み出し、本題に入っていきます。
ワーク(1)「VALUE」
「VALUE」は、普段目にしないようなシチュエーションに対して「いくらもらえたらやるか?」、普段ご両親に買ってもらっているモノに対して「自分ならいくら払うか?」と自分の感覚で金額をつけ、価値観を共有していく探究型のカードゲームです。
それぞれのお金を「もらう」「払う」の価値を比較して「どちらが高いか?」を判断する「HIGH/LOWカード」を使った要素もあり、金銭的な価値の感じ方は人によって異なることに気づくことが、このゲームの魅力となっています。
まずは「チュートリアル」として、簡単なタスクに金額を設定する練習から取り組みました。
非常にリーズナブルな金額をつける子もいれば、「どんなにお金をもらっても絶対にやりたくない。」と答える子もおり、それぞれが自分なりの価値観を正直に表現していました。

ゲームが進む中、2つの値付けを比較して「どちらが高いと思うか?」をチームで考える「HIGH/LOWカード」の場面では、同じチーム内でも意見が分かれる場面が多く見られました。さらに、「風邪をひいていたら?」「時間がなかったら?」といった条件を追加する「シチュエーションカード」が加わると、判断が一転することもあり、価値観が状況によって変化することを実感するきっかけになったようです。
「自分の感覚と他の人の感覚が違うと思った。」
「家族でこのゲームをやってみたい。」
といった声も聞かれ、他者と比べて初めて見えてくる自分自身の金銭感覚に、興味を持つ子どもたちの姿が見られました。
また、ある参加者は金銭感覚の違いに気づいたことで、
「一緒に遊びに行ったとき、たとえば食事に行きたいお店が違うこともあるかもしれない。」
と、日常生活と結びつけた発見を語ってくれたお子さんもいました。
進行のペースもさまざまで、じっくり時間をかけて対話を重ねるチームもあれば、テンポよく話し合いながら進めていくチームもあり、どのチームもそれぞれのスタイルで主体的に取り組んでいました。
ワーク(2)「LOOP」

続いては、「風が吹けば桶屋が儲かる」のように、一つの出来事をきっかけに、その後に起こりうる出来事を連想しながらつなげていく思考ゲーム「LOOP」です。このゲームでは、連鎖の出発点となる出来事を「ステップ1」と定義し、そこから「ステップ2」「ステップ3」…と順を追って自由に展開していきます。
最初のテーマは、普段みんなが飲んでいる牛乳の購入について考えることを出発点に「酪農家が儲かるとどうなるか?」を考えるものでした。
各チームでは、「お金が増える」「働く人が増える」「土地を大きくする」といった経済的な流れを捉えた基本的な展開から始まり、「牛が疲れる」「新しい品種の牛が買える」「機械が進化する」など、ユニークな視点で自由に連想を広げていきました。

2回目のゲームでは、「お金を払うこと」をテーマに、まずは自由にブレスト(ブレインストーミング)を行いました。
最初は苦戦する姿もありましたが、「とにかく思いついたことを全部書く」というアドバイスもあり、徐々にブレストのコツを掴んでいきました。「お菓子を買う」「習い事に払う」「旅行」「人気のレストラン」など多様なアイデアが飛び出し、与えられたテーマに対して積極的に発想を膨らませる姿が印象的でした。
その中から各チームが1つの出来事(ステップ1)を選び、さらに連鎖していく流れを考えていきます。
身近でリアルな視点から、「働く」→「体を壊す」→「病院に行く」→「お金がなくなる」→「また働く」と、まさに『ループ』を表現したチームや、「経済が回ることで環境に影響が出て、地球が大変になる」といったグローバルな視点まで、子どもたちの発想はとても幅広く、その柔軟な思考力にスタッフや保護者達も驚いていました。
多少飛躍する場面もありながらも、各チームとも最終的には「お金」を軸に据えて、しっかりとつながりを持たせたシナリオを完成させていました。

最後は、各チームがつくった「ステップ」を発表し合う時間。
他のチームの発想を聞いた子どもたちからは、
「楽しいことばかりじゃなく、ちょっと怖いこともある。」
といった素直な感想も上がり、まるで人の生涯のようなストーリーを展開させているチームの想像力には、自然と笑い声がこぼれる場面もありました。
それぞれがお互いの発表にしっかり耳を傾け、気づいたことや感じたことを自分の言葉で伝え合う姿が印象的でした。
オープンマイク

イベントの最後には、参加者全員で感想を共有する「オープンマイク」の時間が設けられました。ふでばこをマイクに見立てて、みんなで発表していきます。
子どもたちは自主的に手を挙げて発表に臨むという少し緊張する場面でしたが、はじめに積極的に発言する子に刺激を受けて、周りの子たちにも連鎖する形で多くの子どもたちが自分の言葉で感想を語ってくれました。
子どもたちからは、
「時と場合によっては、お金に対する感じ方が変わることがわかった。」
「お金は身近過ぎて意識していなかったけれど、実は人生に関わるものだと気づいた。」
といった気づきの声が上がりました。
また、ある参加者はこう話してくれました。
「テレビで『みんなで同じ金額に揃えるゲーム』に挑戦しているのを見るたび、『なんでこんなに揃わないんだろう』と思っていたけど、実際に自分でやってみたら、人によって金額の感覚がこんなに違うことがよくわかった。」
体験を通じて実感できた気づきが、言葉として表現されていたのが印象的でした。

また、オープンマイクは保護者側にも移り、我が子に負けじと積極的に発言するご両親の普段見かけない姿に、子どもたちにも相乗効果が生まれていき、ゲームを通して育まれた主体性や他者へ伝える力が自然と表れていました。
保護者の方からは、
「お金のことは学校では学ぶ機会がないので、とても良い機会になった。」
「子どもたちは普段の生活の中で、自然とお金に関する感覚や知識を身につけていることがわかった。」
という声が寄せられました。
学校で学ぶ機会が少ない「お金」というテーマですが、子どもたちは日々の暮らしの中で、すでに多くのことを感じ取り、身につけています。
本イベントは、そうした自然に蓄積された知識や感覚を可視化し、アウトプットするための貴重な場となりました。
イベント企画者インタビュー
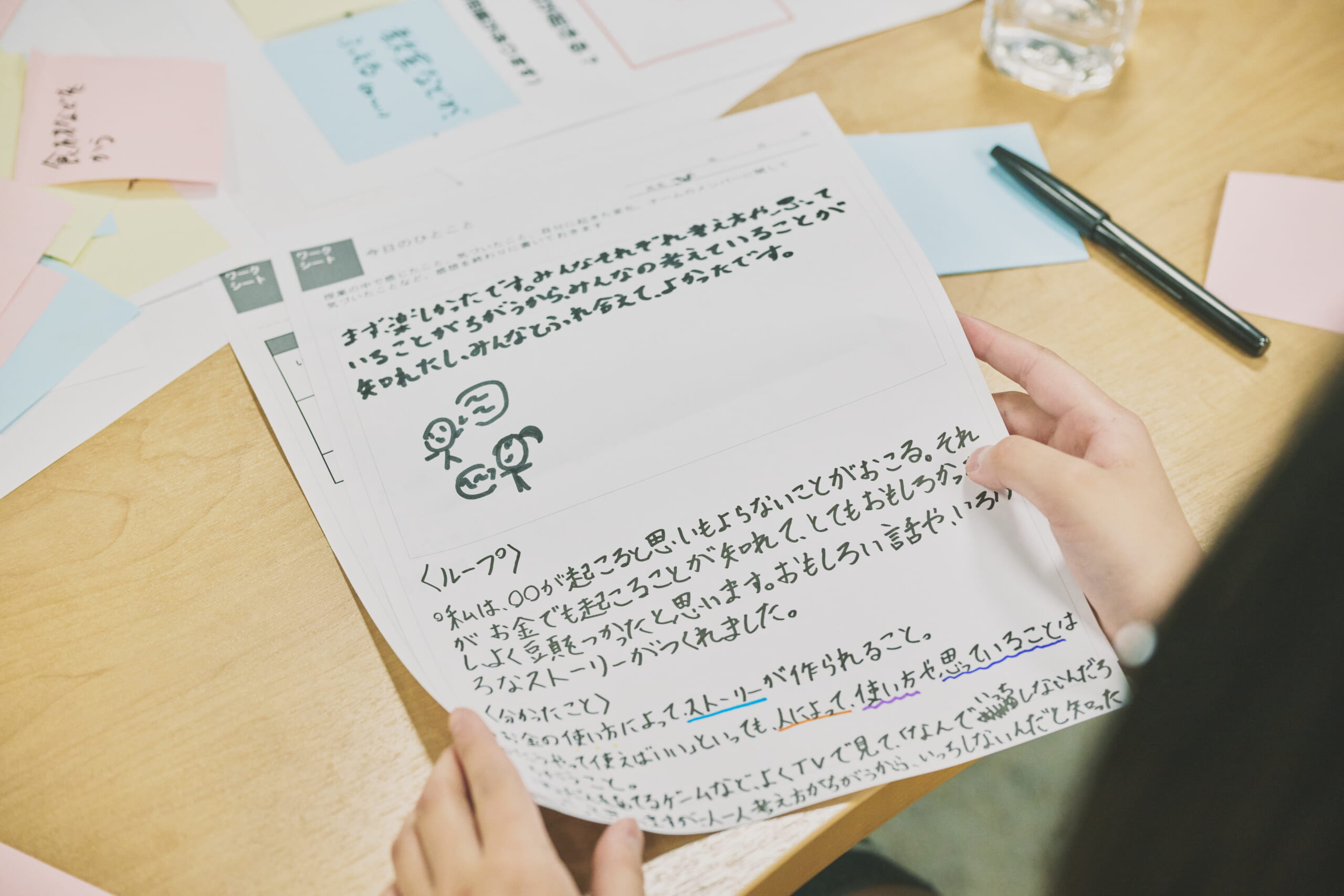
―― 今回の「MONEY GENIUS 2025」を開催するにあたって、どのような狙いや思いがあったのでしょうか?
MUFGは子どもたちへの金融経済教育の推進に積極的に取り組んでいます。
「MONEY GENIUS 2025」は、MUFG金融経済教育の主要プログラムのひとつである探求学習プログラム「VALUE」や「LOOP」を子どもたちに体感してもらい、自分たちの将来に関わるお金という存在をより身近に考えてもらうことを目的としています。
―― 参加者の子どもたちの反応や、印象に残った場面があれば教えてください。
「お金のことをもっと深く知りたいと思った」といった感想が多く、金融機関としてこういった場を提供できたことを嬉しく思います。また、子どもの素直な反応や大人では思いつかなかったような発想があり、子どもたちの柔軟な発想に驚かされました。
―― 今回導入された「LOOP」は、どのような意図で企画されたのでしょうか?また、実際に実施してみての感想や手応えをお聞かせください。
普段、子どもたちがお金を使う場面は、お店でお金を支払うという一方向だけのプロセスですが、「LOOP」については、自分が使ったお金が次はどこにまわり、何を引き起こすのかということを体感いただくことを意図しています。
難しいワークショップだったと思いますが、子どもならではの発想や自由なアイデアが多く、大人では考えつかないような多様な「LOOP」が生まれてきたことが新鮮で、私たちにとっても学びの多いプログラムになりました。
―― 今後の参加型イベントへの展望など。
今後もより多くの子どもたちにMUFGの金融経済教育を届けていくためのイベントを検討中です!是非ご期待ください。

今後もMUFGでは、こうした「主体的に考え、対話しながら学ぶ」探究型の金融経済教育イベントを、学校の授業の中ではもちろん、休日の特別イベントとして継続的に開催し、子どもたちの金融リテラシーを育んでいく予定です。
また次回の開催を楽しみにお待ちください!
ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました。